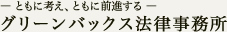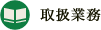多くの人は、自分自身や家族の生活を維持するために、会社に就職して収入を得て生活しています。また、日本に数多く存在する会社は、従業員(労働者)を雇い入れることによって経営を維持しています。
このように現代社会には、会社(使用者)と従業員(労働者)の間の労働関係は無数に存在し、それだけに、労働関係上の様々な法律問題が発生しています。とりわけ、類型的に弱者とされる従業員(労働者)側においては、このような様々な問題に対し、法的な対抗をすることによって自己の権利を擁護していくことが極めて重要です。また、会社(使用者)側においても、労働法上の各ルールを遵守し、従業員(労働者)との正常な関係を形成・維持していくことが、会社の発展にとっても重要な要素といえるでしょう。
典型的な労働問題
1.労働関係の成否(労働者性の有無)に関する問題
1-1. 労働関係の成否(労働者性の有無)が問題となる場合
従業員(労働者)は、会社(使用者)との力関係においては、本来、弱者的地位にあるといえます。そこで、このような当事者間の力関係の不均衡を是正し、対等な労使関係の形成を促すべく、労働基準法や労働契約法などの種々の労働法規が存在し、これによって労働者の権利の確保を実現するための様々なルールが定められています。
しかし、このような労働法上のルールが適用されるためには、働く側と働かせる側の間の関係が「労働関係」であることが必要です。換言すると、両者の間の関係が「労働関係」でなければ、労働基準法の賃金規制や、労働契約法上の解雇規制は適用されないことになります。
したがって、働く側が働かせる側に対して法的な権利を主張しようとする場合、まずは両者の関係が労働関係といえるか(働く側に労働者性を認めることができるか)どうかが重要な問題となります。
このような問題は、とりわけ契約関係に入るにあたって、両者間の契約が労働契約であることを明確に確認する書面が取り交わされておらず、働かせる側が、当事者間の法律関係は請負関係ないし業務委託関係にすぎない(労働者ではなく自営業者である)と主張することによって生じます。
1-2. 労働関係の成否(労働者性の有無)の判断基準
労働基準法上、労働者とは、「使用されるもので、賃金を支払われる者」と定義されており、「使用される」と評価できることと、対価が「賃金」性を有することが、労働者性の要件とされています。
このうち、「使用される」とは、使用者の指揮命令下で労務の提供をしていることを意味し、この指揮命令関係があるといえるか否かは、実務上、概ね次のような観点を重視して判断されています(YESが多いほど労働者性の認定に有利)。
- 1.
- 仕事の依頼や業務従事の指示を断る自由が与えられていない
- 2.
- 業務の内容や遂行の方法について具体的な指揮命令・監督がある
- 3.
- 勤務場所・勤務時間などに拘束がある
- 4.
- 他の人に代わりに業務遂行をさせることが許されない
- 5.
- 機会や器具といった業務遂行のための道具は会社の負担による
また、対価の賃金性については、実務上、概ね次のような観点を重視して判断されています(YESが多いほど労働者性の認定に有利)。
- 6.
- 対価の計算方法や支払形態が他の従業員(労働者性が明らかな者)と同質
- 7.
- 欠勤控除、残業加算があるなど勤務時間に対応して額が変動する
- 8.
- 業務遂行の成果(売上)が支払われる対価の額に直結しない
- 9.
- 事業所得者として確定申告をしていない
- 10.
- 所得税の負担が源泉徴収の形態によっている
- 11.
- 会社を事業所として健康保険、雇用保険に加入し保険料が徴収されている
2.賃金、労働時間に関する問題
2-1. 賃金に関する法律上のルール
賃金は、労働の対価であって、労働者の生活を支える重要なものです。そのような賃金が適正に支払われない場合、労働者の生活には重大な支障が生じてしまうことから、賃金の支払いについては様々なルールが法律(労働基準法)で規定されています。
具体的には、賃金は、原則として、毎月1回以上、一定の決められた日に、支給すべき全額を、労働者に直接、支払わなければならないとされています。2カ月に1回とか、毎月支給される日に規則性がなくバラバラとか、一部を理由なく減額して支給するとか、労働者本人を飛び越して親族に払ってしまうといったことは、原則として許されません。
また、1日8時間を超えて労働を余儀なくされた場合(法定時間外労働)や、法定の休日(※少なくとも週に1日、或いは4週を通じて4日以上の休日を与えることがルール)に出勤を余儀なくされた場合(法定休日労働)などには、所定の労働時間に支払われる通常の賃金額に一定の割合を加算した額(割増賃金)を支払わなければならないことになっています。
さらに、深夜労働(原則として午後10時から午後5時までの間の労働を指す)を余儀なくされた場合にも、割増賃金を支払わなければならないことになっています。
労働基準法上の最低割増率を類型ごとにまとめると次のようになります。
- 時間外労働 ・・・・ 2割5分増し
- 休日労働 ・・・・ 3割5分増し
- 深夜労働 ・・・・ 2割5分増し
- 時間外労働でかつ深夜労働 ・・・・ 5割増し
- 休日労働でかつ深夜労働 ・・・・ 6割増し
ちなみに、通常の1日の就業時間の合計が7時間の会社で、定刻就業時間から1時間後までの残業をしたとしても、労働時間は8時間以内なので法定時間外労働には当たらず、労働基準法の定める割増賃金は支払われません。ただし、このような法定内残業であっても、会社の就業規則で割増賃金の支払いが定められていれば、労働者には所定の割増賃金を請求する権利が生じます。また、休日についても同様に、土日休みが原則の会社で土曜出勤を余儀なくされても、たとえば、この土曜日が労働基準法上の法定の休日に当たらない場合には、労働基準法上の割増賃金は支払われませんが、会社の就業規則で会社の定める休日に出勤した場合の割増賃金の支払いが定められていれば、労働者には所定の割増賃金を請求する権利が生じます。
2-2. 労働時間
賃金は労働の対価ですから、通常は労働した時間に応じて支払われます。したがって、労働時間と賃金は不可分の関係にあるといえます。
もっとも、指示された業務に従事している時間が労働時間に当たることは明らかですが、たとえば、始業時間とされる午前9時からの現場労働に備えて、予め更衣所で専用作業服に着替え、更衣所から現場へ移動する時間や、深夜に仮眠時間が与えられているものの、その仮眠時間中に業務の必要が生じた場合にはただちに出動することが義務付けられている場合に、これらの時間帯も労務提供のために不可欠な時間である以上、労働時間として賃金支払いの対象となるのかといった問題が生じます。
このような問題について、実務上は、使用者の指揮命令関係から解放されていると評価できるか否かを重要な判断基準として、労働時間性が判断されています。
一般的な会社の従業員であっても、就業開始時間は9時だが、8時半からの朝礼への参加が強制されている一方、その30分については賃金の支払いがない、休憩時間として与えられる昼の1時間について、社外飲食が禁止され、電話が入ったら対応することが事実上強制されているといった場合などには、指揮命令関係からの完全な解放があるといえない以上、これらの時間についても労働時間として賃金を請求し得ると考えられます。
2-3. 未払賃金の請求方法
未払賃金がある場合、労働者は当然会社に対してその支払いを求めることができます。ただし、この賃金請求権は、発生から2年で時効によって消滅してしまうので、未払賃金があることが判明したら早期に対応することが重要です。
決められた給料日が過ぎているのに賃金が支払われない、1日8時間を超えて残業しているのに残業時間についても通常と同額の賃金しか支払われていない、といった場合は、できるだけ早めに会社に支払いを求め、それでも会社が支払いに応じない場合には、専門家に相談することをお勧めします。
支払義務が客観的に明らかな未払賃金について、会社がこれを任意に支払わない場合には、労働者は、場合によっては先取特権という特別の権利に基づいて会社の財産(典型的には預金)を直接差し押さえることが可能です。
また、法定時間外労働を行った事実や、時間外労働に対して支払われるべき賃金の具体的計算方法等が争いになる場合も多々ありますが、そのような場合には、会社に対して賃金の請求訴訟を起こすこともあり得ます。ちなみに、訴訟で賃金の未払いが認定され、その支払いを命じる判決がなされる場合、賃金未払いに対する一種の制裁として、実際の未払賃金額に付加して一定の金銭(付加金)の支払いが命じられることがあります。
3.配転命令(配置変更・転勤等)に関する問題
会社においては、必要に応じて、労働者に対し、配置変更や転勤の命令がなされます。これは、使用者たる会社が有する業務命令権の行使といえます。
しかし、使用者であるからといって、これらの配転命令を無制限に行うことは許されません。
たとえば、会社とある労働者との間で、採用時に職種や勤務地を限定する内容の特約が明確になされていた場合には、会社は、事実上の必要が生じても、その労働者に対して配転をすることはできません。
また、そのような職種・勤務地等の限定に関する特約がない場合であっても、配転命令が不当な動機・目的をもってなされたものである場合や、配転によりその労働者が被ることとなる不利益の程度が、通常甘受すべき程度を著しく超える場合などには、会社による配転命令は、権利の濫用として違法・無効なものとなるとされています。権利濫用として配転命令が違法・無効と認められる場合には、労働者はもとの勤務部署・勤務地で働き続けることができます。
なお、配転命令を拒んだ労働者を、これを理由に業務命令に反したものとして解雇するという場合もあり得ますが、前提となる配転命令が違法・無効であれば、そのような配転命令を拒絶することは正当な行為であることから、上記のような理由によってなされた解雇も権利濫用として違法・無効なものとなります(まさに解雇が客観的合理性を欠く場合といえるでしょう)。
4.解雇・雇止めに関する問題
解雇は労働者に対する究極的な不利益処分であり、その適法性、有効性が認められるためには、厳しい要件を充足していることが必要です。また、有期雇用契約において、契約期間満了時に契約を更新せず、雇止めとする場合についても、労働者の地位そのものを剥奪するものであることから、一定の制限が課せられています。
したがって、労働者が、使用者から、法律や判例によって課されている制限に反して、解雇・雇止めを受けた場合には、その解雇・雇止めは違法・無効であるとして、労働者たる地位を主張して、就労の継続と賃金の支払いを求めることができます。
以下では、解雇・雇止めについての法的な制限の概要を紹介します。
4-1. 解雇
解雇には、いくつか種類がありますが、大きく分けると、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3つがあります(このほかには、たとえば諭旨解雇などもあります)。
それぞれの解雇については、以下のような制約があるとされています。便宜的に順番を入れ替えて説明します。
4-1-1. 懲戒解雇
懲戒解雇は、懲戒処分(懲戒解雇・諭旨解雇・休職・出勤停止・減給・戒告、訓告、譴責など)のうち、労働者にとって最も厳しい懲戒処分といえます。懲戒処分は労働者の非行(企業秩序違反)に対する制裁であり、いわば刑罰のようなものですから、その中で最も重い処分である懲戒解雇には、次のような各要件が必要とされています(分類は一義的ではありませんが、概ねこのような要件が必要と解されます)。
| 1.就業規則への規定 | どのような場合に懲戒解雇となり得るかを予め就業規則に明記して、労働者に周知しておかなければならない。 |
|---|---|
| 2.規定の合理性 | 就業規則に定められた懲戒解雇事由はそれ自体合理的なものでなければならない。 |
| 3.懲戒事由たる事実の存在 | 就業規則に定められている懲戒事由に該当すると認められる事実が存在していなければならない(認定できる客観的事実が懲戒解雇事由に該当するものでなければならない)。 |
| 4.処分の相当性 | 労働者が行った非行の性質、内容、程度に照らし、懲戒解雇という究極的懲戒処分をもって対処することが相当といえなければならない(他の懲戒処分では対応できないと評価できる場合でなければならない)。 |
| 5.処分の公平性 | 先例等に照らし、労働者の非行に対して懲戒解雇を行うことが公平といえなければならない(先例に照らせば同様の非行については、減給等のより軽度の懲戒で済んでいるにもかかわらず、差別的に懲戒解雇を行ってはならない)。 |
| 6.二重処罰・遡及適用の禁止 | 同一の非行について二重に制裁を課す形での懲戒解雇は許されず、かつ、新たに就業規則に規定された懲戒事由を改訂前の労働者の行為に遡って適用して解雇することは許されない。 |
| 7.適正な手続の履践 | 懲戒解雇を行うためには、労働者に対し、弁明の機会等が与えられなければならない。 |
4-1-2. 整理解雇
整理解雇とは、労働者に落ち度があるわけではなく、業績悪化や経営不振といった使用者側の都合で人員を削減しなければならない場合に行われる、リストラとしての解雇です。このような整理解雇については、以下のような各要件が必要とされており、これらのいずれかを欠く場合は、たとえ整理解雇としてなされた解雇であっても無効となるとされています。
| 1.人員削減の必要性 | 客観的にみて、人員削減が必要な程度の経営危機等が現に存在しなければならない(たとえば、整理解雇の一方で新卒者を大量に採用しているといったような場合には、人員削減の客観的必要性があるとはいえない)。 |
|---|---|
| 2.解雇回避努力措置 | 解雇以外のより軽度の措置(残業削減、出向、新卒採用中止、希望退職者募集等々)を検討せずに、直ちに整理解雇をすることは許されない。 |
| 3.人選の合理性 | 被解雇者の選定は、客観的、合理的な基準に沿って行われなければならない。 |
| 4.手続の妥当性 | 使用者は、労働者に対し、整理解雇に関する十分な説明を行い、誠意をもった協議を行わなければならない。 |
4-1-3. 普通解雇
以上のような特殊な解雇に当らない解雇、たとえば、労働者が肉体的、精神的に業務に耐えることができない状況となったことを理由に行われる解雇などを普通解雇といいます。このような普通解雇についても、法律上、制限が課されており、労働基準法18条の2や労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。
具体的には、(1)普通解雇事由に該当する事実の存在と、(2)相当性(解雇以外の対処ではありえないと評価できること)が必要といえるでしょう。
ただし、通常、会社の就業規則には、普通解雇事由を定める条文と懲戒解雇事由を定める条文が別途規定されているところ、解雇事由が趣旨として両者で共通しているということはよくあります。その場合、いったん懲戒解雇を行った会社は、解雇の適法性・有効性を主張する中で、懲戒解雇として適法・有効でなくとも、(懲戒解雇に比べると要件の厳格性が劣る)普通解雇として適法・有効であると主張する場合があります。しかし、経緯や実態に照らして、あくまで懲戒解雇の趣旨で行ったと認められる場合には、解雇の単なる形式にかかわらず、より厳格に適法性、有効性が判断されるべきといえるでしょう。
4-2. 雇止め
有期労働契約(契約の期間に限定が付されている労働契約)については、予め期間を契約で定めて合意した以上、期間満了時に会社が労働者の雇用を継続しないという判断をすることは自由なようにも思えます。しかし、有期労働契約であっても、過去に何度も更新され、労働者が以後も当然に更新されるものと期待することが自然な場合には、結局、雇止めは労働者にとって解雇と同一の意味を有することになります。そこで、これまでの過去の裁判例では、有期雇用契約における雇止めであっても、一定の場合には、これを許されないとの判断をしてきました。このような裁判例の蓄積を踏まえ、労働契約法19条が新設され、雇止めを制限する法理が明文化されました(平成24年8月10日公布・施行)。
労働契約法19条は、具体的には、以下の内容を規定しています。
| 1.対象となる有期雇用契約 | a. 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの |
|---|---|
| b. 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの | |
| 2.労働者からの更新希望意思の表明 | a. 労働者が有期雇用契約の期間満了日までに契約更新の申し込みをした場合 |
| b. 労働者が有期雇用契約の期間満了後、遅滞なく有期雇用契約の締結の申し込みをした場合 | |
| 3.雇止めの合理性、相当性 | 有期労働契約が上記(1)のいずれかの類型に該当し、かつ上記(2)のいずれかの事実が存在する場合に、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めは許されない(=「使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす」) |
5.退職強要、いじめ、パワハラ等
上記4では、実際に会社から解雇がなされた場合の規制について紹介しましたが、労働者が退職を余儀なくされるケースとして、退職強要と呼ばれるものがあります。退職強要とは、その名のとおり、労働者に対し、その真意に反して、自ら退社するよう不当に強要することです。強要の類型には、直接的に退職を求めるケースの他、いじめや、パワハラ等によって間接的に退職へ追いやるケースもあり得るでしょう。
解雇には上記のような厳格な制限があることから、最終的な退職の形式として労働者が自ら退職を申し出たということにして、解雇規制の潜脱を図ろうとするケースが実際に存在します。
しかし、このような退職強要(或いは組織的ないじめ、パワハラ等自体)は、法律上不法行為に該当することから、違法な退職強要を前提とする退職の意思表示の効力はこれを争うことが可能な場合があるほか、退職強要行為それ自体によって被った精神的損害の賠償を求めることも可能な場合があります。もっとも、退職強要行為は、通常、会社という閉鎖的環境において行われることから、実際に退職強要行為としてどのような嫌がらせや言動があったのかについては、これを具体的に認定できる証拠が必要ということになります。
問題の解決手段とポイント
1.解決手段
1-1. 交渉
以上のような労働問題が現に発生した場合、その解決手段としては、第1次的には、弁護士に事件処理を委任するなどして、相手方と交渉し、妥当な解決を目指すという方法があります。交渉の段階で、紛争が訴訟等に発展した場合の法的な結論について、当事者間である程度認識の共有が実現すれば、早期円満解決もあり得ます。
1-2. 訴訟
交渉によって和解解決が実現しない場合には、法的手続によって、自己の主張する権利を確定させることとなります。一般に、法的手続の典型としては、訴訟があります。
訴訟においては、自身が主張する事実について、これを認めるに足りる証拠を提出するとともに、証拠によって認められる事実によって自己の主張する法的権利が発生するということを説得的に論じる必要があります。
労働問題に関する訴訟で、特に解雇等の有効性を争う訴訟など労働者の地位自体に関わるものについては、長期化することが多いといえるでしょう。
1-3. 労働審判
以上のような訴訟の他、労使間の紛争に関する特殊な紛争処理制度として、労働審判という制度があります。訴訟との違いの概要は以下のとおりです。
- 1.
- 裁判官(労働審判官)だけではなく、労使間の問題について専門的な知識と経験を有する労働審判員が手続に加わり、労働審判官1名と労働審判員2名で構成する労働審判委員会が判断をする。
- 2.
- 原則として3回の期日のうちに一定の結論(和解又は審判)に至ることとされている。
- 3.
- 公開の法廷ではなく非公開の部屋で行われる。
- 4.
- 当事者の主張・反論は、書面ではなく、期日における口頭でのやりとりを基本とする。
- 5.
- 和解が成立しない場合には、判決でなく労働審判が言い渡され、審判の内容に不服がある当事者が異議を申し立てることによって通常の訴訟に移行する。
2.手続選択のポイント
上記の解決手段のうち、特に訴訟に比べた場合の労働審判の最大のメリットは、短期間での一定の紛争処理が制度的に予定されているところといえるでしょう。しかし、一方で、労働審判に対しては当事者が不服を申し立てることで通常の訴訟に移行するとされていることから、原則3回の期日のうちに和解による解決が実現せずに労働審判から訴訟に移行した場合、最終的な解決までにより多くの時間を要する結果となることもあり得なくはありません。
また、主として口頭でのやり取りを基本とし、かつ、金銭和解による紛争解決を基本とする労働審判制度の性質上、紛争の内容が労働審判に適しないケースもありえます。そのような場合には、最初から訴訟を提起する方が賢明でしょう。
したがって、いずれの法的手続を選択するか否かは、相手方との事前交渉の内容・経緯や紛争そのものの性質といった事情等を総合的に考慮して判断するべきでしょう。
使用者たる企業におけるコンプライアンス
以上のように労使間に発生し得る法的な問題は多岐にわたるとともに、これらの紛争は一度発生すると直ちに解決することが難しい場合が少なくありません。また、そのような紛争が生じること自体が、企業に対する社会的信用を傷つけることにもなりかねません。
そこで、企業においては、常にコンプライアンス(法令遵守)に気を配り、適正な労務管理等を実現することが非常に重要といえるでしょう。
もっとも、労使関係に関する法的ルールのみをとっても、その内容は決して簡明とは言えないため、場合によっては、法的なルールを見落としてしまった、或いは、周りでもそうしているから法的に許されていると思い込んでいたなどといったこともあり得ると思われます。
そのような不備によって労使間の紛争が生じることのないよう、企業においては、予防法務の観点から、法律の専門家に助言を仰げる体制を設けておくことが望ましいといえるでしょう。